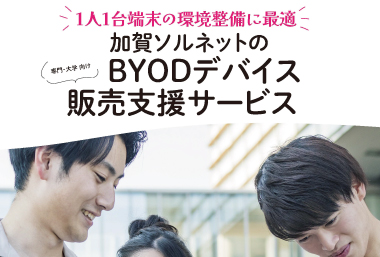学生必見!Mac?Windows?後悔しないパソコン選びのポイント
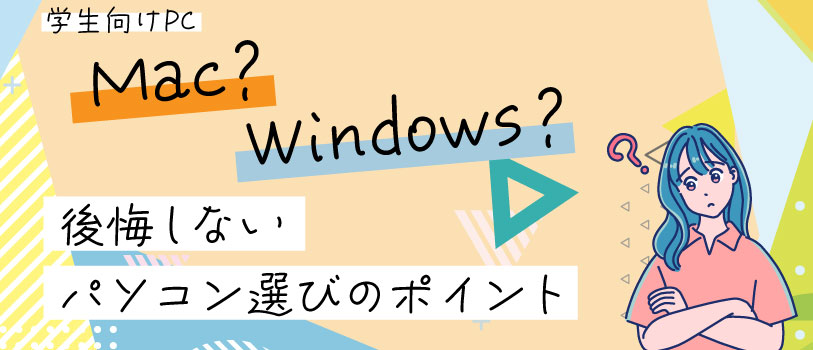
大学や専門学校への進学を控えた学生にとって、入学時に大きな悩みとなるのが「パソコン選び」です。特に「MacとWindowsのどちらを選ぶべきか?」は多くの学生や保護者が迷うポイント。
実際に学校から「推奨PCリスト」が配布されることもありますが、用途や学部、将来の進路によって最適な選択は異なります。さらに近年は社会人になってからもBYOD(Bring Your Own Device:自分のPCを業務に利用する)が広がりつつあり、学生時代に選んだパソコンがそのまま社会人生活に影響するケースも増えています。
そして日本では、スマートフォンユーザーの多くがiPhoneを利用しているという背景もあり、Macとの親和性が高い環境にある学生も多くなっています。
データやスペック傾向をもとに、学生パソコンとしてのMacとWindowsの違いを徹底比較し、あなたの学部や将来の目標に合わせた最適な選び方を解説していきます。
目次
学生向けパソコンのリアルなトレンド
学生が選んでいる主流スペックを見てみましょう。以下のような傾向があります。
【WindowsPCの主流スペック】
多くの大学・専門学校で販売・利用されているWindowsPCのスペックは、以下の通りです。
- ●CPU: Intel Core i5
- ●メモリ: 16GB
- ●ストレージ: SSD 512GB
※当社調べによる傾向
この構成は、WordやExcel、PowerPointといったOfficeソフトの利用、Webブラウジング、オンライン授業、そして一般的なプログラミング学習など、学業のほとんどの用途で快適に動作します。以前はメモリ8GBも一般的でしたが、最近のOSやWebブラウザは多くのメモリを消費するため、複数のアプリケーションを同時に立ち上げても動作がもたつかないよう、16GBが事実上のスタンダードになっています。SSDの512GBも、課題や写真、動画などのデータを十分保存できる安心の容量です。
【MacBookシリーズの主流スペック】
多くの大学・専門学校で販売・利用されているMacBookシリーズのスペックは、以下の通りです。
●CPU:M4
●メモリ: 16GB
●ストレージ: SSD 512GB
※当社調べによる傾向
MacもWindowsと同様、メモリ16GB、SSD512GBが主流です。Apple独自のM4チップは、従来のIntel製チップと比較して圧倒的なパフォーマンスと省電力性を両立しており、特に動画編集や画像編集といったクリエイティブな作業でその真価を発揮します。バッテリーの持ちが非常に良いのも大きな魅力です。
【情報系、建築系、映像・3Dデザイン系の主流スペック】
より高度な作業を要求される学生の中には、一般的なスペックを上回るパソコンを選ぶ方も増えています。
●CPU: Intel Core i7
●メモリ: 16GB
●ストレージ: SSD 512GB
●GPU: RTX 4050 GPU(ゲーム制作・3DCG・映像学科など)
※当社調べによる傾向
ゲーム開発、3DCG、動画編集、AI学習など、CPUやGPUに負荷のかかる作業には、高性能なCore i7や、専用のグラフィックボード(GPU)であるNVIDIA® GeForce RTX™ 4050が不可欠です。これらのパーツは、重い処理をスムーズに行い、作業効率を飛躍的に向上させます。
■学生向けパソコンの主流スペック
| 機種 | Windows | MacBook | Windows(GPU) |
| CPU | Intel Core i5 | M4 | Intel Core i5 |
| メモリ | 16GB | 16GB | 16GB |
| ストレージ | 512GB | 512GB | 512GB |
| GPU | – | – | RTX 4050 GPU |
※当社調べによる傾向
このように用途によって、最適なスペックは大きく異なります。
まずは、自分が何にパソコンを使うのかを具体的にイメージしてみましょう。
Mac vs Windows 徹底比較!
MacとWindowsのそれぞれの特徴を、また学生に人気のスマートフォン、iPhoneユーザーの視点も交えて深く掘り下げていきます。
Windowsの強みと弱み
■Windowsの強み
圧倒的な汎用性と互換性
パソコン市場の約80%以上を占めると言われているWindowsは、大学や企業、公共機関など、ほとんどの場所で使われています。そのため、ソフトウェアや周辺機器の選択肢が非常に豊富で、互換性の問題に悩まされることはほとんどありません。
特に理系・工学系・情報系の学部では、授業や研究で使用する専門ソフトの多くがWindows環境を前提に開発されています。特定のソフトはMacでは動作しない、または仮想環境が必要な場合が多く、Windowsならそのまま使える安心感があります。学部や用途に関係なく、「必要なソフトが確実に動く」という点は、パソコン選びにおいて非常に大きなメリットです。

多様な選択肢とコストパフォーマンス
Lenovo、NEC、Panasonic、マウスコンピューター、富士通、Dell、HP、など、多くのメーカーがWindows搭載パソコンを販売しています。デザイン、性能、価格帯も多岐にわたり、自分の予算や好みに合わせて最適な一台を見つけやすいのが魅力です。Macと比較して、同スペックでも安価なモデルが多く、コストパフォーマンスを重視する学生にとっては大きなメリットです。
自由なカスタマイズ性
Windowsパソコンの最大の魅力は、自由度の高さと拡張性です。特にBTO(受注生産)メーカーでは、CPU・メモリ・ストレージ・GPUなどを自分の用途や予算に合わせて自由にカスタマイズできるため、理系・クリエイティブ・ゲーミングなど、幅広いニーズに対応可能です。
また、多くのWindowsノートPCはメモリやストレージの増設が可能で、購入時に予算を抑え、必要になったタイミングで性能をアップグレードするという柔軟な運用ができます。
さらに、周辺機器との互換性が非常に高いのも特徴です。プリンタ、スキャナ、外付けGPU、USB機器など、ほとんどの製品がWindowsに対応しており、導入や設定もスムーズです。
■Windowsの弱み
セキュリティリスク
利用者が多い分、ウイルスやマルウェアの標的になる可能性が高いのがWindowsの宿命です。セキュリティ対策ソフトを入れていないと、怪しい広告をクリックしただけで不審なプログラムが入り込み、動作が遅くなることもあります。情報リテラシーに不慣れな新入生の場合、知らないうちに危険なサイトへアクセスしてしまい、個人情報や学内アカウントを盗まれるリスクも否定できません。
学校によっては「セキュリティ対策ソフト必須」としているところも多く、Macよりも管理の手間が増えるのが現実です。
メーカーによって品質が異なる
Windowsパソコンは選択肢が豊富なことが魅力ですが、その裏返しとして品質に大きなばらつきがあるのもデメリットです。安価なモデルではディスプレイの視野角が狭く、少し角度を変えると文字が見づらい、色合いが正しく表示されないといった不満につながります。
また、キーボードの打ち心地やタッチパッドの精度が低いモデルも少なくなく、長時間レポートを書く学生にとっては疲労の原因になります。結果として「購入時は安いけれど、結局使いにくくて買い替えを検討する」という事態に陥りがちです。
経年使用での動作低下
Windowsはハードウェアとソフトウェアの組み合わせが多様であるため、使い続けるうちに動作が重くなる傾向があります。特に安価なモデルでは、2〜3年使うと起動に時間がかかる、ファンが常に回ってうるさい、複数のアプリを開くと固まるといった症状が出やすいです。
一方でMacは、同じマシンを4〜5年使っても比較的快適に動くことが多く、リセールバリュー(中古販売価格)も高いため、結果的にトータルコストで差が出ることがあります。Windowsも高性能モデルなら長く使えますが、「予算を抑えたつもりが結局数年で買い替え」というパターンは学生にとって負担になりやすい弱点です。
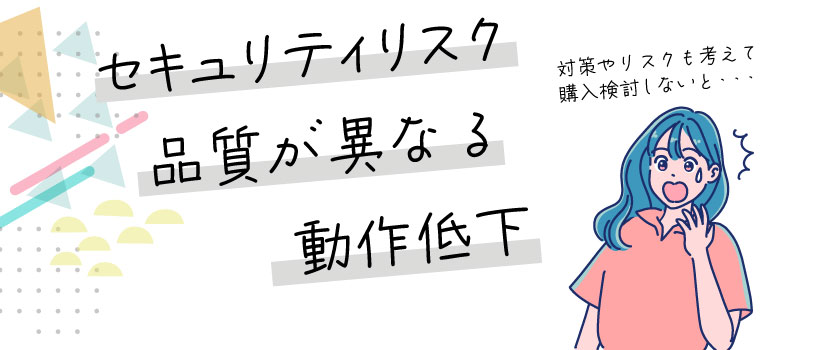
Macの強みと弱み
■Macの強み
日本のスマートフォン市場では約7割がiPhoneユーザーと言われています。もしあなたがiPhoneを使っているなら、Macの最大の強みはこれに尽きます。
iPhoneとのシームレスな連携
例えば、たとえば、授業中にiPhoneで撮影した板書や実験データの写真を、わざわざケーブルで接続したりクラウドにアップしたりせず、AirDropで数秒以内にMacへ転送できます。レポート作成の途中でも、スマホで取った画像をすぐにWordやPagesに貼り付けられるため、時間のロスがありません。
また「Handoff」機能を使えば、iPhoneで途中まで作成したメールやメモを、Macでそのまま続きから編集することができます。課題提出やゼミの準備で、移動中はiPhone、自宅ではMacという使い分けが自然にできるのは大きな利点です。メッセージや着信もMacで受けられるため、オンライン授業中や資料作成中でもスマホを手に取らずに対応できるのも便利です。
iPhoneを普段使いしている学生にとって、Macは単なる「パソコン」ではなく、生活の延長線上にある学習ツールとして自然にフィットします。毎日の小さな便利さが積み重なり、結果的に学習効率や作業スピードの向上につながる点は、Windowsには真似しづらいMacならではの強みといえるでしょう。
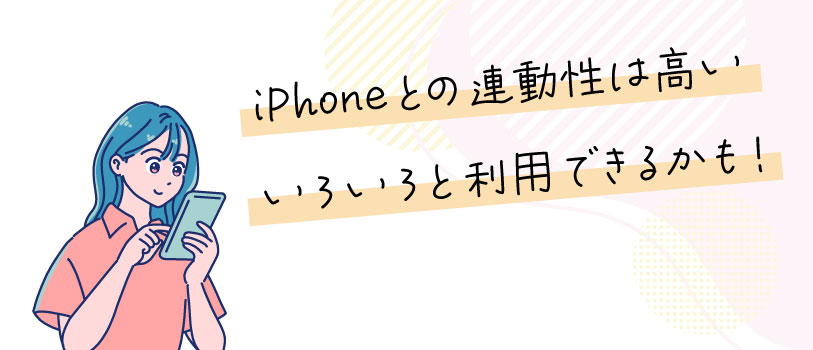
洗練されたデザインと直感的な操作性
Macを手にしたときにまず感じるのは、無駄のないシンプルで洗練されたデザインです。薄型で軽量なボディは持ち運びやすく、大学のキャンパス内を移動するときもストレスを感じません。アルミ削り出しのユニボディは高級感があり、長時間使っても手に馴染む質感を持っています。見た目の美しさはもちろん、強度と耐久性を兼ね備えているため、学生生活の4年間をしっかり支えてくれる存在になります。
そして、Macのもうひとつの大きな魅力が直感的に使える操作性です。macOSのインターフェースはシンプルでわかりやすく、マルチタッチトラックパッドを使ったジェスチャー操作は、慣れると「戻る」「アプリ切り替え」「拡大・縮小」が指先ひとつで思い通りにできます。これにより、授業で複数の資料を開きながらノートを取る、調べ物をしながらレポートを書くといった作業が非常にスムーズになります。
さらに、デザインやUI(ユーザーインターフェース)の完成度が高いため、PC初心者でも比較的迷わず操作を覚えられる点も見逃せません。余計なアイコンや複雑な設定画面に煩わされることなく、「やりたいことにすぐ取りかかれる」ことは、勉強や制作のモチベーションを保つうえで大切なポイントです。
高いパフォーマンスと省電力性
Appleが自社開発したMシリーズチップは、WindowsのCPUとGPUを統合したような性能を持ち、非常に高い処理能力を発揮します。これにより、動画編集やプログラミング、デザイン作業などが驚くほど快適に行えます。省電力性能も非常に優れており、一日中バッテリーが持つモデルも珍しくありません。
■Macの弱み
ソフトウェアの互換性
Macはデザインや動画編集などのクリエイティブ分野に強みを持つ一方で、理系・工学系・情報系の学部では注意が必要です。事前に学校のホームページなどで確認が必要です。特に専門ソフトは、Windows環境を前提に設計されていることが多く、Macでは動作しない、または仮想環境(例:Parallels、Boot Camp)を使う必要があります。
授業や研究で頻繁に使われるため、Macでは不便を感じる可能性が高く、結果的に授業の進行に支障をきたしたり、同級生との作業に差が出ることもあります。また、Officeファイルの互換性にも注意が必要です。Windowsで作成したWordやPowerPointのファイルをMacで開くと、レイアウトが崩れるなどのトラブルが起こることがあります。
本体価格が高め
同等スペックのWindowsノートPCと比べると、Macは価格が1.2〜1.5倍ほど高い傾向があります。
特に「メモリ16GB/SSD512GB」といった学生利用に十分な構成にすると、20万円前後になることも珍しくありません。長期間使える耐久性やリセールバリュー(中古売却時の価値)は高いのですが、初期投資として大きな負担になる点は無視できません。
拡張性が低い
Macは「購入時にスペックを決めたら、その後の増設や改造ができない」設計です。特にAppleシリコン搭載モデルはメモリもストレージも基盤に直付けされているため、後から「容量が足りないから増やしたい」と思っても不可能です。そのため、購入時点で将来を見据えたスペック選びが必須となり、結果的に価格がさらに高くなる傾向があります。
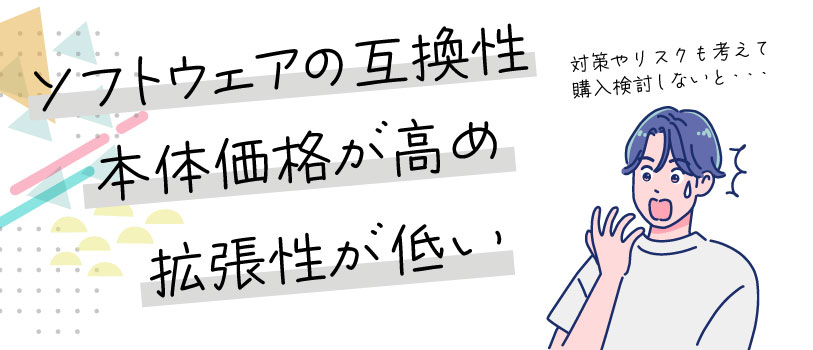
MacとWindowsの違いを比較
| 項目 | Windows | MacBook |
| デザイン・操作性 | 多様なメーカー・デザインも幅広い 操作はOSによってやや複雑 | シンプルで直感的 トラックパッド操作が快適 |
| 平均価格帯 | 幅広く選べる(10~25万円台) ※GPU搭載パソコンは高額 | 比較的高め(15~30万円台) |
| 対応ソフト | Office、研究系・工学系ソフトに強い (CAD、統計、プログラミング等) | Adobe系、動画・音楽編集など クリエイティブ分野に強い |
| 学部 | 理系:◎(研究・開発ソフトに必須) 文系:〇(コスパ重視) ゲーミング・専門:◎ | 文系:〇 (レポート・資料作成+iPhone連携) 芸術・デザイン系:◎ |
| iPhone連携 | 連携は限定的。OneDriveや Google Driveを併用するケースが多い | AirDrop、Handoff、iCloudで シームレスに同期 |
| 社会人での活用 | 企業シェア多数。特に大企業 研究開発系ではWindows標準 | 広告・デザイン・出版 ベンチャー企業で利用率高い |
※当社調べによる傾向
学部別! あなたに最適なパソコンの選び方
ここからは、あなたの学びたい分野に合わせて、どちらのパソコンがより適しているかを具体的に見ていきましょう。

文系学部・経済学部・教育学部など
【おすすめPC】WindowsまたはMac
レポート作成、プレゼンテーション、オンライン授業など、学業の基本的な用途ではどちらのOSでも問題ありません。大学の授業ではMicrosoft Officeを使う機会が多いので、互換性の面でWindowsが安心という声もありますが、最近はMicrosoft 365もMac版が充実しており、大きな差はありません。
どちらを選ぶかは、デザイン性や操作性の好み、予算、そしてあなたがiPhoneユーザーかどうかで決めるのが良いでしょう。
理系学部・工学部・情報科学部など
【おすすめPC】Windows
高確率でWindowsをおすすめします。 多くの研究室や学科で使う専門的なシミュレーションソフトや、実験機器を制御するソフトウェアはWindows環境での動作が前提となっています。特に、CADソフトや回路設計ソフトなどはMac版がない場合が多く、せっかく買ったMacが授業で使えない、ということになりかねません。
デザイン・芸術系・建築学部など
【おすすめPC】MacまたはWindows(高性能モデル)
MacのMシリーズチップは、Adobe Creative CloudのPhotoshop、IllustratorやFinal Cut Proなど、クリエイティブ系のソフトウェアで非常に高いパフォーマンスを発揮します。
しかし、3DCGや建築デザインの分野では、Windowsが有利になる場合もあります。これは、Windowsには高性能なGPU(グラフィックボード)を搭載したモデルが豊富にあるからです。
特に、NVIDIA® GeForce RTX™ 4050などのGPUは、レンダリングや映像制作の時間を大幅に短縮してくれます。クリエイティブな作業をする上で、どちらのOSにもメリットがあります。使用予定のソフトウェアがどちらのOSに対応しているか、体験版で試してみるのも良いでしょう。
医療・看護・薬学部など
【おすすめPC】Windows
電子カルテシステムや医療系の専門ソフトウェアは、Windows環境で動作するものが主流です。大学のPC教室や実習室もWindowsがほとんどなので、スムーズに学習を進めるためにもWindowsを選ぶのが無難です。
「とりあえず安く済ませたい」とこれらのモデルを購入してしまうと、入学後すぐに動作の遅さに悩まされたり、容量不足で外付けストレージを買い足す必要が出てきたりする可能性があります。結局のところ、買い替えることになったり、追加費用がかさんだりするケースも少なくありません。
学生時代から考える!社会人でのPC事情
近年、企業におけるパソコンの支給方法は多様化しており、従来の「会社が一括で支給する」スタイルから、従業員が自分で使いたいPCを選べる『従業員選択制』へと移行する企業が増えています。
この制度では、業務に必要なスペックやセキュリティ要件を満たしていれば、WindowsでもMacでも選択可能なケースが多く、社員の働き方や職種に応じた柔軟な選択が可能になります。
多くの企業で使われている業務システムやツールはWindows環境で動くものが多いため、Windowsが主流です。しかし、デザイナーやエンジニアなど、専門職の分野ではMacの使用が許可されることもあります。この制度を考えると、学生時代から自分がどのOSを使い続けたいのか、将来のキャリアを見据えて考えることが重要になってきます。学生時代に慣れ親しんだPCをそのまま仕事で使えることは、大きなメリットとなるでしょう。

万が一に備える「サポート」という選択
弊社調査統計情報の中で、特に注目すべきなのは、学生の約9割が何らかのサポートサービスに加入しているという事実です。これは、学生生活においてパソコンがどれほど重要なツールであるかを示しています。
うっかり落として画面を割ってしまった。コーヒーをこぼしてキーボードが動かなくなった。急な故障でレポートが提出できない…。学生生活では、このようなトラブルがいつでも起こり得ます。修理費用は高額になることが多く、予期せぬ出費で困ってしまうことも少なくありません。
メーカー保証は基本的に「自然故障」のみが対象です。物損や盗難は保証対象外となるケースがほとんどで、修理費用は自己負担となります。画面割れや水濡れの場合、修理費用が数万円〜10万円以上かかることもあり、せっかく購入したのに、結果的に高額な出費になってしまうことも。
しかし、学校が販売するPCには安心のサポート体制が整っていることがほとんどです。
延長保証サービスの特徴
●物損も盗難もカバーなど
●修理上限額が回復する「上限回復型」など
●充実のサポート内容
※各種サービス内容によって異なります。
弊社で提供しているオリジナルの延長保証サービスは、メーカー保証ではカバーされない水濡れや落下、盗難など、より幅広いトラブルに対応していることが多いです。万が一のトラブル時も、専門のスタッフが迅速に対応してくれるため、学業への影響を最小限に抑えることができます。
【 物損も盗難もカバー】
多くの市販PCの保証では対象外となる「水濡れ、落下、破損」といった物損事故も、手厚く保証してくれます。また、万が一の盗難にも対応しているプランもあるため、通学や外出先でも安心してPCを持ち運ぶことができます。
【 修理上限額が回復する「上限回復型」】
「修理回数無制限」「修理費用上限額は購入金額まで」という保証はよく見かけますが、一度高額な修理をすると、残りの上限額が少なくなってしまうことが課題でした。このサービスでは、「修理上限額が回復する」という画期的な仕組みを採用しており、何度修理しても安心です。
結論:初期費用だけでなく、4年間の安心を考えれば、手厚い保証が付いた大学PCのメリットは計り知れません。
MacとWindows、究極の選び方
MacとWindows、どちらを選ぶかは、「何に使うか、将来何をしたいか」 そして「そのためにどのような環境が最適か」 で決めるのが一番です。
【 迷ったら「Windows」が無難】
多くの大学・専門学校の環境に対応でき、ソフトウェアや周辺機器の選択肢も豊富。コストパフォーマンスも高く、初めてのパソコンでも安心して使えます。
【 明確な目的があるなら「Macbookシリーズ」】
デザインや音楽制作、プログラミングなど、Macの強みを活かせる分野を志すなら、最高のパートナーとなってくれるでしょう。特に、iPhoneとの連携を重視するなら、Macがおすすめです。
あなたの新生活の第一歩を後押しする一助となれば幸いです。素敵な学生生活を送ってくださいね!
結論:どちらを選んだとしても、メモリ16GB / SSD512GBというスペックは
最低限確保しておいた方が良いです。
また、万が一のトラブルに備えて延長保証サービスに加入しておくことを強くお勧めします。
この記事に関連する資料
こちらもおすすめ
-

学内文書の認印回覧は 3ステップでOK!
学内の業務文書の押印回覧、みなさまどうされてますか?ワークフローシステムをすでに導入されてる学校もあると思いますが、「紙で押印回覧」という学校もまだまだ多いのではないでしょうか?
-

次世代避雷システム「dinnteco」
落雷現象を“発生させない”構造で、学校キャンパスやグラウンドなど最大半径100mを1台でカバー、防護ゾーンを実現します。
-

学生募集マーケティングに役立つ MAツールはAdobe Marketo Engage
年々減少している学生数ですが皆様、学生募集で苦戦されてはいませんでしょうか?今後も学生の減少が進むと予想されている中、今までと同じ手法で学生を集めるのは厳しいとされています。その中で近年、マーケティングオートメーションが注目を浴びています。