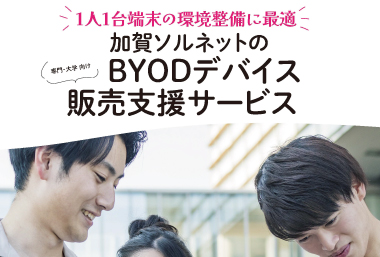日本電子専門学校グラフィックデザイン科様

前身であるコンピュータデザイン科として1997年に設立。紙媒体中心の情報伝達を目的としたデザインに加え、時代ごとに社会のニーズを汲み取りながら、求められるデザインの形を模索し、広告、雑誌、ポスター、パッケージ、ゲーム、Web、スマートフォンアプリなど幅広いフィールドにおけるグラフィックデザインのワークフロー全体を修得できるカリキュラムを有している。入学直後のワークショップでデザインの考え方や基礎を学べるので、未経験者にも安心な指導が受けられる環境であり、企業との連携授業等を通して、デザイン業界で即戦力として活躍できるデザイナーの育成を目標としている。 多くの授業で使用するiMacが教室設備の中心であり、6色のカラー展開で見た目も鮮やかな教室で学ぶことができる。
社会人基礎力というのは、コミュニケーション力やプレゼンテーションといった意思の疎通を通じて学んでいくもの
【お話を伺った先生方】
植田誠一先生(グラフィックデザイン科科長)
井上順子先生(グラフィックデザイン科)

グラフィックデザイン科ではどのようなことを学ぶのでしょうか?
(植田先生)
専門学校自体が職業教育と社会人基礎力を育む二本の柱で成り立っていると考えていますが、グラフィックデザイン科ではそれぞれの柱とも重要なものと捉えています。社会人基礎力というのは、コミュニケーション力やプレゼンテーションといった意思の疎通を通じて学んでいくものだと思います。職業教育の方で言うと、近年デジタル媒体が増加したことでグラフィックの領域がとても広がったように感じています。従来の紙媒体でのポスター、チラシ、パッケージに加え、UIやUX、デジタルサイネージや電子書籍などの電子媒体も増えてきていますよね。つまり、ただ作るだけではなく、どうすれば商品が売れるのかであったり、見た目だけではなく企画力が問われたりと様々な方向から学んでいく必要がある学科だと思います。
(井上先生)
グラフィックデザイン科設立時は紙媒体の学習に特化した学科でしたが、時代の変化に応じ、現在は電子媒体を含め広範囲に学べるようカリキュラムを設定しています。 デザインというと自分の世界観を表現するものと思われがちですが、本校ではユーザーのためのデザインということを意識しており、ユーザーがどのような環境や目的で媒体を目にするかを想像しながら作品を作れるデザイナーになれるよう教育活動を展開しております。

グラフィックデザイン科創立の経緯を教えていただけますでしょうか?
(植田先生)
1997年にコンピュータデザイン科として発足したのが始まりで、その頃はグラフィックデザインコースとWebデザインコースの二つのコースに分かれていました。そこからグラフィックデザイン科とWebデザイン科に学科が分かれ、現在28年目になります。
現在、学科自体は分かれていますが、グラフィックデザイン科で学んだ学生が就職後にWebデザインに携わることもあるので、Webデザイン制作という授業科目も残しています。学科の人数自体は多くはないですが、学生に占める専任教員の数が多いので、目が行き届きやすい体制が構築できていると思います。

時代の変化によって学ぶ内容も変わってきているのでしょうか?
(井上先生)
学科開設当時の1997年はDTP黎明期であったので、DTP技術を習得することに重きを置くカリキュラムを設定していました。一方、現在はAIの台頭もあり、人間に求められる役割である企画力の養成に重きを置くようなカリキュラムに変化しています。
また、現在浸透しているデザイン思考について、本校は専門学校の中でもその浸透に早期からに力を入れてきました。グラフィックデザイナーの仕事の領域が拡張するのとともに、デザイン思考を身につける必要性を感じ、浸透させていけるよう教育活動を展開した経緯があります。
(植田先生)
ここ数年ではコミュニケーションデザインやモーショングラフィックスといった授業が新たに誕生しました。グラフィックの分野ではWebも関係してくるので動画作成の授業を取り入れましたし、授業の名称は変わらないものの、中身が大きく変化した科目もあります。今後は、アート要素を含めてとにかくモノを作るといった授業も新たに展開していく予定です。
どのように時代が変化していくのか先を想像しながら教員側でカリキュラムを作成しています。
グラフィックデザイン科として大切にしていることはありますか?
(植田先生)
情報デザインというキーワードを科全体で据えています。それぞれの専門性を持って教員が教育活動を行っておりますが、全教員に共通しているのはユーザー中心といった考え方になります。デザインにも様々種類があるのですが、グラフィックデザインにおいてはユーザーに情報を伝えるということが一番大事であると意識してもらえるよう教育活動を展開しています。
入学当初、自分の足でどの場所にどのような広告物が展開されているのかを話題となっている店舗に出かけるフィールドサーベイという授業があります。そこでなぜそのデザインが話題になっているのか、その環境に身を浸し自分自身で考えてみるといった活動をしています。その後のステップとして、後期にインフォグラフィックスを学びます。
二年生に進級後は、一年時に学んだことをエディトリアルデザインに活かしたり、デジタルサイネージですとかスマートフォンとかのUIデザインにも学びを展開していったりします。デジタルの場合は、 必要な情報をわかりやすく伝える必要があるとともに情報自体を目で捉えてもらうことが必要になります。また、見えているものの裏側にどのような情報があるかを想像させるような、情報設計といったところまで展開しています。情報を収集、整理、構築した上で設計することを二年前期までに学び、学んだ内容を二年後期にある卒業制作で活かせるよう教育内容を考えています。

企業から学生に出された課題に対して、実際に企画・制作を行い、最終的に企業相手にプレゼンテーションを実施
特徴的な授業はありますでしょうか?
(植田先生)
学校としても学科としてもですが産学連携授業が挙げられると思います。必修授業でパソコンやソフトの使い方を学び、実際にそれらが企業でどのように使われているのかはこの産学連携授業で学ぶことができます。
企業から学生に出された課題に対して、実際に企画・制作を行い、最終的に企業相手にプレゼンテーションを実施します。従来は作品のビジュアルに重点が置かれていましたが、現在は企画段階から何を売りにしてどう魅力を伝えるか、頭を使って考える必要があります。足を使って現地調査をするなど作品を作り出すまでに相当な時間をかけて取り組んでおり、学生も頭を抱えているようですが、その過程を大事にしていることが本科の強みかもしれません。
企業で企画がどのように立てられ、どのような流れで商品ができていくのかも学べますし、対外的な評価や自分自身の立ち位置も知ることができます。一線で活躍しているデザイナー様や企業などから実務を学べるだけではなく、コミュニケーション能力や社会人基礎力も学ぶことができる基幹的な科目になっています。
産学連携授業で授業を担当する講師はどのような方ですか?
(植田先生)
デザイン会社の方が講師となるケースが多いです。産学連携授業のために特別に設定いただいた課題でも、出来栄えが良いものがあれば授業とは別にプロジェクトを組んでいただき実現に向けて進めていくケースもありました。そこから就職に結びついた学生もいますので、学生にとって実務に直結するため、達成感を感じられる授業であると思います。
(植田先生・井上先生)
他にも2年次の後期に設置している科目で業界研究という授業があります。卒業を控え社会に出ていく学生を対象とする社会に出ていくための準備のような内容となっており、外部から講師を招き、現在のデザインの潮流や業界事情などを講義してもらっています。
最近ですとAIなど最先端のキーワードについてゲストとなる講師と一緒に授業を組み立てました。内容として充実しているものであれば、通年の授業に落とし込むこともあります。
卒業後の進路はどのような職種を希望する方が多いでしょうか?
(植田先生)
割合として一番多いのはグラフィックデザイナーです。その他の進路は多岐に渡りますが、例えばDTPデザイナーやオペレーター、UI/UXデザイナーも多いですね。在学中に学んだ知識と得られたコミュニケーション能力を生かして、営業職に就く学生もいます。直近ではAIクリエイターに就いた学生もいます。グラフィックデザインの領域自体がすごく広いので、多様な進路を選択できることも学科の特徴であると思います。
パッケージを作りたいですとか、イラストレーターになりたいですとかピンポイントで将来これをやりたいといって入学する生徒が多いのですが、在学期間中に自分の得手不得手を理解していくことで進路が決まっていく印象です。

印象的な学生はいらっしゃいましたでしょうか?
(植田先生)
学力レベルの高い大学に入学ができるにも関わらず、早くに技術を習得して社会で活躍したいとの思いから本校へ入学を選んだ学生がいました。入学先の選び方も多様になってきている印象があり、最近入学する学生は自分自身の考えを持って入学している印象が強く、目的があり将来を見据えているような方が多い印象です。
(井上先生)
学生との関係でいうと、学生とともに新しいことに取り組み、日本デザイン学会等で発表するという機会があります。教員と学生という関係性はあるものの、目的を共感することができるのでお互いの関係性を深める一助となっています。そこで関係を深めた学生は先ほどお話した産学連携授業のクライアント側で来てくれたり、こちらが依頼すると講話をしてくれたりと色々な形で卒業後も学校に関わってくれたりもしています。
どのような学生に入学をしてほしいという思いはありますか?
(井上先生)
学ぶ意欲と素直さがある学生が入学してくれるといいなと思っています。素直な学生が一番成長しますし、そのような学生が多く集まると競争も生まれ相乗効果をもたらすと考えます。
(植田先生)
様々なコンテストや大会がありますので、受け身ではなく主体的な学びの姿勢やチャレンジ精神を持った学生が入学すると有意義な二年間を過ごすことができると考えます。

Apple製品について
iMacの活用方法とは?
デザインの世界でMacが使用されている理由はどこにあるのでしょうか?
(井上先生)
MacとAdobeの親和性というのが理由の一つかもしれません。PhotoshopやIllustratorがWindowsに対応していなかった時代があるので、印刷会社などではそれらに対応しているMacから導入し始めていたようです。本校のグラフィックデザイン科においても、デザイン業界と同じような環境で学習をした方が良いだろうとの思いから、学科設立当初からMacを使用しております。
(植田先生)
Macを使用することは業界の慣習のようになっています。産学連携授業でお越しになる講師の方も皆さんMacを使用していますし、私たちも社会人基礎力を育むための教育機関として業界に合わせた形でMacを使用しています。
Macは色再現が優れていると感じていますし、iPhoneを持っている学生にとって画像などのファイルやデータ連携もしやすいことがメリットかと思います。デザインの世界では作成したデータをやり取りすることが必須となりますので、スピーディーにデータをやり取りできるApple製品はとても優れていると思います。
iMacを活用する授業は全体でどのくらいの割合なのでしょうか?
(植田先生)
実習の授業ではほぼ必須で、授業全体を通じても7割くらいに達するのではないでしょうか。Macを使用しないのは鉛筆を使って手書きでデッサンをする時や、画材を扱うような授業の時くらいです。
iMacを使用して学んだことが有利になるケースはあるのでしょうか?
(井上先生)
学科の特性上就職先でもMacがある環境が多いので、学生時代から職場と同じ環境で学べることがメリットだと考えます。

Macを使って学んだ学生に対し期待することはどのようなものでしょうか?
(植田先生)
Macを使用することでモチベーションが上がり、苦手な作業があっても、前向きに作業ができるような感覚が持てると良いと思います。
Mac教室について
教室に6色のiMacが並んでいますが、何か意図があったのでしょうか?
(植田先生)
特徴的な教室を作りたかったというのが1番の理由になります。色というのはデザインに大きく関わってきますし、グラフィックデザイン科にとってのキーワードになるものであると思います。クリエイティビティとかクリエイティブ力とか発想力といったものに色は不可欠な要素であると思いますし、多くの色を並べることによって無意識のうちにクリエイティブ力が育まれる側面があると思います。
結果的に見栄えもとても良いものですし、多くの方のインパクトに残るものとなりました。
実際にこの光景を見た方の反応はどのようなものでしょうか?
(植田先生)
体験入学でお越しになった方にとても綺麗ですねと言っていただける機会が増えました。詳しい方だと全色揃っていることに気づく方もいらっしゃいますね。カラーが複数あることで、他の学科の教室と雰囲気が異なることを感じとっていただけています。
(植田先生・井上先生)
学内の職員だけではなく、他学科の学生もガラス越しにiMacを見て羨ましそうにしていました。
入学検討者や見学に来る高校の先生方にも良い印象を与えているようです。
見た人の目にも強く印象が残りますし、カラフルなデザインで目立つこともあってか学生も意識的に教室を綺麗に使ってくれるようになったと感じます。

BYOD販売サービス「アカデミコナビ」について
Apple製品の供給において信頼をおいている
導入業者として加賀ソルネットを選択し、満足いただいている点と今後期待する点を教えていただけますでしょうか?
(植田先生)
連絡も密に取っていただいて滞りなく進めていただいている印象です。学校のスケジュールはタイトな側面がありますので、スケジューリングを意識していただき、連携を取りながら今後もサポートいただけますと嬉しいです。
(井上先生)
Apple製品の供給において信頼をおいております。教育や学校というものを深く理解していただけており、要所要所で新しい技術の紹介や学生にとっての有益な情報、アプリケーションの情報などを提供していただいております。ただ物を売るだけではなく、サービスも一緒に提供していただける点がありがたいと感じています。今後期待するということよりも継続していってほしいというのが願いです。